公認会計士・税理士の藤沼です。
2014年にEYに入社し、その後2018年にコンサル職に転職 → 2019年に会計事務所を独立開業しました。
独立から早5年が経過し、本当に色々なことが見えてきました。
実は私自身、もともと独立するつもりがありませんでした。
かなり見切り発車的に独立したため、「もっとこんな経験をしておけば良かった…」という後悔(?)も少し感じています。
そこで今回は、将来独立を考えている会計士向けに、おすすめの転職先とその選び方を紹介します。
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入社
2018年 東京共同会計事務所 入社
2019年 藤沼会計事務所 開業
2020年 アカウントエージェント株式会社 代表取締役
会計士が独立開業した後に関与するサービス
私たち会計士が独立した後に関与する可能性のあるサービスは、大きく次の2種類あります。
それぞれ、もう少し具体的に解説します。
税務|独立開業した後ほぼ確実に関与するサービスライン
多くの場合、会計士は独立後(または独立前)に税理士資格登録を行い、税務サービスを提供します。
独立開業した会計士が提供する一般的な税務サービスは、次のとおりです。
- 記帳代行
- 決算業務
- 税務申告
- 税務顧問
- その他、税務アドバイザリー
顧客は個人・法人様々ですが、最初は顧客獲得が容易な個人から請け負うケースが多いです。
初めから中小企業クライアントのみをターゲットにしても良いですが、社長個人の確定申告もセットで請け負うケースがあるため、結局は所得税に触れる必要があります。
また、独立後に触れる可能性のある税目は次のとおりです。
関与する可能性のある税目
- 法人税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
- 所得税
- 相続税
- その他、国際税務など
税務は、会計士受験生時代の座学としての知識も役立ちますが、実務家として、税務官の視点や判断の慣行などを知っておかなければなりません。(これが税理士の優劣に大きく影響)
そのため、税務サービスを提供するのであれば、会計事務所での経験はほぼ必須です。
なお余談ですが、転職先によっては税理士登録を禁じているケースがありますので、サラリーマン時代に税理士登録する際には必ず組織に確認しましょう。
コンサル|M&AやIPOなどは利益率が高くオススメ
会計士が提供する代表的なコンサルサービスは、次のとおりです。
- M&Aコンサル
- IPOコンサル
- 経営コンサル
もちろん、この他にもニッチな分野も含めれば多種多様です。
M&Aコンサルでは、主に財務DD及びバリュエーションを請け負います。
IPOコンサルでは、一人で関与するケースもあると思いますが、1つのプロジェクトチームにコンサルタントとしてアサインされることが多いでしょう。
そして経営コンサルですが、ふたを開ければ財務分析+α程度のサービスであることが多いです。
いずれも、一般的なFASで経験できる業務が多く、(経験値は必要ですが)会計士にとってはさほど難易度の高い業務ではありません。
ただし、コンサルのみで会計事務所を回すのは(最初は)難しいと感じます。
会計士の独立開業に適した転職先
会計士の独立に適した転職先は、次の2種です。
もちろん、戦略コンサルやBIG4系FASでも独立できないことはないですが、一般的ではありません。
それぞれ解説します。
会計事務所|独立開業を見据えた会計士に1番おすすめの職種
会計事務所は、独立志向の会計士に最もオススメできる転職先であると断言できます。
なぜなら、次のようなメリットがあるからです。
- 税務実務を学ぶことができる
- 会計事務所の経営・運営を間近で見て盗める
- 何なら、経営会議にも参加できる
- 会計事務所の損益構造・採算性が把握できる
- 会計事務所の営業方法が分かる
- スタッフの採用方法が分かる
会計事務所の開業後は、税務サービスに重きをおく必要があり、税務実務を学ぶためにも会計事務所での経験はほぼ必須でしょう。
また 会計事務所で働くことで、会計事務所での経営・人事・総務すべてが分かります。
実は、税務スキル以上にこの運営スキルが重要であり、これは実際に間近で見なければ身に着けることが難しいでしょう。
私は独立後にすべて自分で調べて身に着けましたが、1~2年かかりました。
なお、会計事務所に転職した会計士の働き方については、会計事務所に転職した会計士の「キャリア」とメリット・デメリットで詳しく解説しています。
独立系FAS|コンサルで稼げるがスポット業務である点には注意
FASにも色々ありますが、先述のおりM&A・IPOの経験できる独立系FASをオススメします。
独立志向の会計士が独立系FASを選ぶメリットは、次のとおりです。
- 複数のFASを横断的に経験できる
BIG4系FASでは、サービス品質が高いというメリットがありますが、1つのサービスラインに特化することになるため独立にはやや不向きであると感じます。
一方、独立系FASでは、財務DD・バリュエーション・PMIなど多くのサービスラインに関与できるのが一般的であり、独立後に必要となるスキルを多く身に着けることができます。
ただし、FASでは税務顧問等に従事できるケースがほぼないため、この点はFASのデメリットとも言えるでしょう。
なお、FASに転職した会計士の働き方については、FASに転職した会計士が「仕事内容」「キャリア」を分かりやすく解説で詳しく紹介しています。
「既存の会計事務所を事業承継する」という選択肢もある
ここまでは、あくまで転職により独立開業のためのスキルを磨き、その後自ら会計事務所を独立開業する、という前提で話を進めました。
しかし、実は独立にはもう1つ選択肢があり、それが「開業税理士から事務所を事業承継する」という選択肢です。
日税連のアンケート調査によれば、開業税理士の平均年齢は60歳を超えています。
開業税理士の年齢分布と平均年齢
| 年齢 | 中央値 | 件数 | 割合 | 積数 |
|---|---|---|---|---|
| 20代以下 | 20歳 | 25 | 0.1% | 0.03 |
| 30代 | 25歳 | 772 | 3.2% | 1.13 |
| 40代 | 35歳 | 3,285 | 13.7% | 6.17 |
| 50代 | 45歳 | 4,849 | 20.3% | 11.14 |
| 60代 | 55歳 | 6,947 | 29.0% | 18.86 |
| 70代 | 65歳 | 6,493 | 27.1% | 20.34 |
| 80代以上 | 80歳 | 1,572 | 6.6% | 5.58 |
| 計 | 23,943 | 100% | 63.3歳 | |
60代で働いている開業税理士が最も多く、開業税理士の高齢化が進んでいることが分かります。
つまり、今後事業の承継に頭を悩ませる税理士が増えると考えられるでしょう。
また同様に、日税連のアンケート調査によれば、事業承継により事務所を開業している税理士は 全体の約12% 存在することが明らかにされています。
開業税理士の開業形態
| 回答件数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 自ら開業 | 20,321 | 84.6% |
| 事業承継 | 3,474 | 14.5% |
| (内、親族からの承継) | 1,494 | (6.3%) |
| (内、勤務先からの承継) | 726 | (3.1%) |
| (内、その他) | 738 | (3.1%) |
| (内、無回答) | 61 | (0.3%) |
| 計 | 24,767 | 100% |
割合は少ないものの、「勤務先の所長から事業承継により事務所を引き継ぐ」という選択肢もあることが分かるでしょう。
つまり、後継者を探している会計事務所に入所し、事業を引き継ぐという選択肢もあるのです。
事業承継のメリット|新規開拓が不要で売上も安定して発生
会計事務所を引き継ぐことのメリットは、次のとおりです。
- 既に顧客が存在するため、新規の営業先を開拓する必要がない
- ほぼ売上が約束されているため、路頭に迷う心配がない
- 所長交代後は、自由に顧客を選定できる
会計事務所を引き継ぐ場合、基本的には将来のキャッシュインフローがほぼ確定しています。
そのため収益面でのリスクが小さく、業務を適切に引き継ぐことさえできていれば、路頭に迷うこともないでしょう。
また、所長交代後は自らが全ての意思決定を行うことができるため、たとえば不要な顧客を切るといった選択も可能でしょう。
事業承継のデメリット|途中で撤退しづらく事務所の縮小も難しい
会計事務所を引き継ぐことには、デメリットも存在します。
- 徐々に業務を引き継いでいくため、途中で辞めづらい
- 交代前に事務所の名称が変わることも多く、途中で辞めづらい
- 事業を縮小したくなった場合、スタッフをクビにすることができない
事業承継には、大きなデメリットがあります。
それは、「途中で事務所を辞めづらい」というデメリットです。
後継者ポジションとして転職すると、所長交代を見据え、少しずつ業務を引き継ぐことになります。
また、事務所名に後継者の名称を入れるなど、交代前に自分の名前が看板に載るケースが多く、もし途中で辞めたくなっても非常に切り出しづらいのです。
以上のように、「やっぱり辞めた」ができず、自分の将来が(良い意味でも悪い意味でも)敷かれたレールに乗ることになります。
また、既に大きくなった事務所の顧客を整理したい場合であっても、既に雇用しているスタッフを自由にクビにすることができません。
事業承継による事務所開業を見据える場合には、必ず、上記のリスクを見据えるべきです。
まず非常勤として働いて徐々に会計事務所を拡大するという選択もある
私が最近よく目にするのが、まず監査法人で非常勤職員(業務受託者)として働きながら、会計事務所を徐々に拡大していくという方です。
非常勤だけで生計を立てるフリーランスの公認会計士もいるくらいです。
つまり転職を経ず、いきなり監査法人から独立するという選択です。
リスクが大きいようにも見えるかもしれませんが、実はメリットもあります。
というのも、特に非常勤職員の多い中小監査法人では、同様に会計事務所を開業している会計士も多く、クライアント・案件を紹介してもらえるケースがあるからです。
実際、私も業務受託者として働いていた中小監査法人内で、新たな仕事を紹介してもらうことがありました。
逆に、私の会計事務所では専門外となるクライアントについては、同チームの会計士に紹介したりしていました。(手数料等は取りません)
また、先述のとおり中小監査法人での非常勤自体も、かなり儲かる仕事です。
時給単価は平均7,000円であり、中には時給10,000円の求人まであります。
がっつりアサインされれば、簡単に年収1,000万を超えるため、最近はこのような働き方にシフトする会計士も増えています。
なお、監査法人での非常勤については、公認会計士の非常勤、小さなデメリット vs 大きすぎるメリットで詳しく解説しています。
公認会計士が独立開業した後の年収イメージ
私の年収を明かすわけにはいかないので、客観的な根拠を示した上で、会計士が独立した場合の一般的な年収イメージを紹介します。
まずは初年度~3年目までの目標として、年収2,000万辺りを狙うと良いと思います。
内訳は、次のようなイメージです。
- 税務:400万
- 監査法人での非常勤:300万
- FAS:1,300万
あくまで例示ですが、このくらいであれば無理のない水準でしょう。
※ 寝る間も惜しんで働けば年商3,000万まではいけると思いますが、それ以上は従業員が必要になるケースが大半です。
非常勤については、日給5万、年間60日勤務を想定しました。
税務の報酬については、日税連による開業税理士の年収アンケート調査が参考になります。
根拠を示します。
まず、日本税理士会連合会は、開業税理士の年収に関するアンケート調査を実施しています。
開業税理士の年収金額分布
| 年収(総所得金額) | 全回答者に対する分布 |
|---|---|
| 300万以下 | 26.0% |
| 300万~500万 | 16.9% |
| 500万~700万 | 12.6% |
| 700万~1,000万 | 15.5% |
| 1,000万~1,500万 | 13.9% |
| 1,500万~2,000万 | 7.3% |
| 2,000万~3,000万 | 5.3% |
| 3,000万~5,000万 | 1.8% |
| 5,000万~1億 | 0.6% |
| 1億超 | 0.1% |
| 平均年収 | 約871万円 |
年収分布としては300万円以下が中央値ですが、平均年収としては871万円です。
会計士には他の業務もあるため、低く見積もって税務では500万程度をまず目指すと良いでしょう。
FASについては私の肌感覚が入りますが、税務クライアントからのアドバイザリー依頼等により、年間500万程度であれば無理のない範囲であると感じます。
あくまで私の考え方ですが、まずは税務を軸にするのがオススメです。
というのも、税務顧問により最低限の報酬を維持し、またクライアントのコネクションを口コミによって増やすことができるからです。
完全単発のFASにばかり力を入れていると、関与するクライアントの数が少なくなってしまい、中々コネクションが広がらないのです。
税務顧問は原則継続契約ですから、安定収入にもなります。単価は低いですが、マーケティングの一環として請け負っておくべきだと感じます。
独立志向の会計士が転職先を選ぶ際の視点
会計士として独立開業を目指す場合の転職先について、選ぶ際の視点を紹介します。
それぞれ解説します。
所長が「公認会計士」の会計事務所を選ぶ
かなりオススメです。
私たち会計士は税理士とは異なり、「企業会計に強い」という優位性をもっています。
そのため、税務だけではなく、できれば税務+FASの経験できる会計事務所をオススメします。
FASにも関与できる会計事務所(≒所長が会計士の事務所)を選ぶことで、税務+FASを経験することができるでしょう。
所長が会計士の事務所では、FAS・税務にバランス良く関与できる可能性があります。
自分が目標とする規模の会計事務所を選ぶ
一言に「会計事務所」といっても、規模はピンキリです。
5名以下のスタッフから構成された会計事務所もあれば、100名を超える中堅会計事務所もあります。
将来的に、会計事務所の規模をそこまで大きく拡大する予定が無い方は、5~10名程度の会計事務所が良いと感じます。
転職する会計事務所の規模が小さいほど、近い将来の自分を重ねてイメージすることができるからです。
未来の自分をイメージしながら働くことで、業務からより多くの知見を吸収できるようになるでしょう。
自分が得意・好きなサービスラインで転職先を選ぶ
好きこそ物の上手なれと言いますが、本当にその通りだと思います。
好きな分野・得意な分野であれば、ストレスが少なく、競合事務所との差別化も容易になります。
そのため、既に自分が得意とする・好きなサービスが存在する方は、当該サービスに強い会計事務所を選ぶと良いかもしれません。
一方、まだ得意分野・好きな分野が定まっていない方は、全般的なサービスを経験できる転職先を選ぶと良いでしょう。
市場ニーズの強いサービスラインで転職先を選ぶ
先述した開業後のサービスラインは、あくまで市場規模の大きなサービスラインです。
一方、市場規模が小さくとも市場ニーズは強いフィールドもあります。
転職先を探す際、どのような市場ニーズが存在するのかリサーチし、同時に当該組織の年収も聞き出すことで、市場ニーズの強さをある程度予測することができるでしょう。
一見ニッチでニーズの無さそうな分野であっても、提示された年収が高い場合、市場ニーズの強さが年収に反映されている可能性が高いです。
特に、市場を独占しているようなサービスラインがある場合、独立後に当該サービスを提供することで、クライアントを横取りすることもできるでしょう。
なお、各求人のサービス詳細や、具体的に提示される年収については、必ず転職エージェントから入手しましょう。
求人サイトなどで公開されている情報は、一般的なサービス・年収であるケースが多く、個別具体的な詳細が示されていないからです。
独立志向の会計士の転職に関するよくある疑問
その他、独立志向の会計士の転職先について、よくある疑問をまとめてみました。
40代での独立は遅いですか?
全く遅くありません。
先述のとおり、開業税理士の平均年齢は60歳を超えています。
スキルさえあれば、独立開業に年齢は関係ないと感じます。
また、体力的な面を気にされる方も多いと思いますが、独立後安定すると、ストレス・体力的な負担はかなり減ります。
開業資金はどのくらいあれば良いですか?
必要ありません。
私たちには「非常勤」という最強の選択肢があり、生活費はほぼコレで賄えるからです。
オフィスは自宅またはバーチャルオフィスを活用することで、初期費用はほぼかかりません。
独立に向いている人はどんな人ですか?
強いて言えば、ゼロから自分で考え行動できる人は向いていると思います。
逆に、上司の指示に忠実なタイプの人は、あまり向いていないと思います。(かなり偏見が入ってます)
独立開業は楽しいですか?
今は楽しいです。会社員時代のようなストレスがほとんどなくなりました。
ただし、独立してから半年~1年ほどはストレスが地獄でした。
私は見切り発車で独立したこともあり、生きていけるかどうかも分からない状況だったからです。
そのため、皆さんには十分な準備をしたうえで独立開業してほしいです。
地方での独立は難しいですか?
正直、やりようだと思います。
もし私が地方で開業をした場合、おそらく東京よりも楽に稼ぐことができると思います。
もちろん、地方では既に地域密着型の会計事務所がクライアントを囲っています。
しかし、それでも新規クライアントを確保する手段はいくらでもあります。
公認会計士の転職先にはどのような職種がありますか?
公認会計士の転職先は、全13種に分けられます。
- 経理
- 内部監査
- 経営企画
- ベンチャーCFO
- 大手監査法人(アシュアランス)
- 大手監査法人(アドバイザリー)
- 中小監査法人
- FAS
- 戦略コンサル
- 会計事務所
- 税理士法人
- 投資銀行
- PEファンド
公認会計士の転職先について、詳しくは次の記事内ですべて解説しています。
独立志向の会計士におすすめの転職エージェント【比較表】
| マイナビ 会計士 | MS-Japan | ヒュープロ (Hupro) | レックスアド バイザーズ | ジャスネットキャリア | |
|---|---|---|---|---|---|
 |  |  | |||
| 総合評価 | ( 10/10 ) | ( 8/10 ) | ( 8/10 ) | ( 7/10 ) | ( 7/10 ) |
| 求人数 | 約5,000件 | 約1,500件 | 約1,300件 | 約1,000件 | 約500件 |
| 対象年代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 |
| 対応エリア | 関東 近畿 愛知県 静岡県 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 設立 | 1973年 | 1990年 | 2015年 | 2002年 | 1996年 |
| 資本金 | 21億210万円 | 5億8600万円 | 2億2740万円 | 6000万円 | 3800万円 |
| 特徴 | 公認会計士限定 | 管理部門に強い | 会計事務所に強い | 士業全般向け | 会計税務全般 |
| 得意領域 | 公認会計士 | 経理 監査法人 FAS | 経理 会計事務所 | 会計・税務 コンサル | 士業全般 |
| 評判口コミ | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る |
| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
公認会計士が転職エージェントを使うなら、マイナビ会計士1択です。
なぜなら、唯一会計士専門のエージェントであり、私たち会計士向けの求人数がNo.1だからです。
先述のとおり、独立開業には監査以外の経験が必須です。
独立後のサービスラインをリサーチする為にも、まず転職エージェントに登録することをお勧めします。
\ 会計士向け求人数 No.1! /
/ かんたん3分で登録完了 \
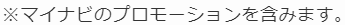
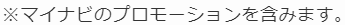

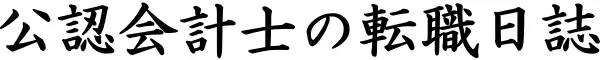
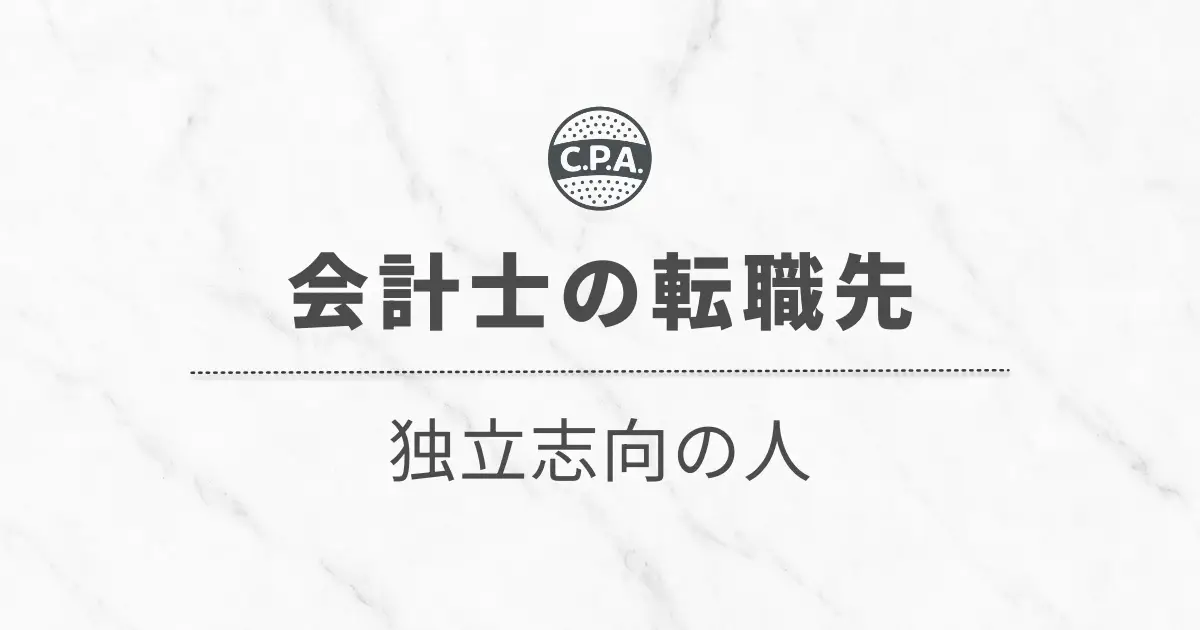

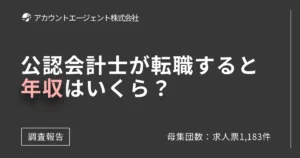
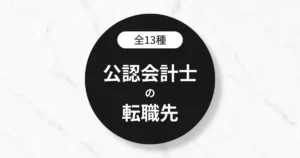
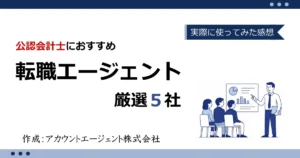
コメント